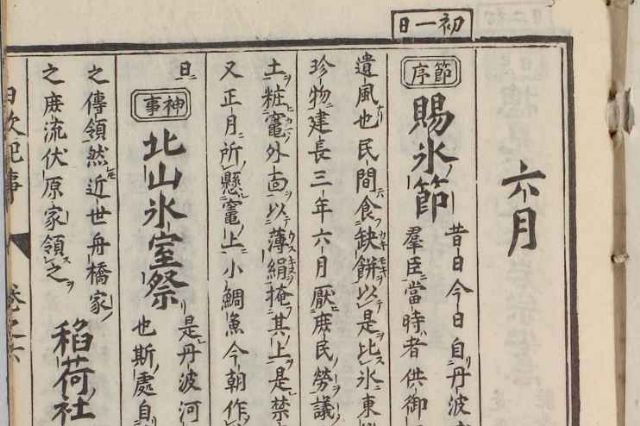スピーチと、そのスピーチの主というものは、親子のようなものではないかと思う。
あきらかに強い関係で結ばれてはいるが、完全な一体だとは言えない。時が経つとともに、親が子を忘れることもあれば、子が親よりも偉大になる場合もある。双方が背を向けることだってあるだろう。
オバマ氏が広島を訪れ、広島平和記念資料館を参観し、17分のスピーチをしてから10日ばかりが過ぎた。この間、日本国内では消費税率の引上げの再延期の決定があり、参院選挙日程の確定があって、5月27日もすこし遠くなってしまったが、このいま、オバマ氏の広島訪問とそのスピーチについて考える。
むろんのことこの件については、(人によっては訪問の以前から)さまざまな論評がなされた。肯定的なもの、否定的なもの、いずれも種々の歴史、事実、背景と引き比べて論評しているので、わたしなどは大変に勉強になる。
そうやって勉強になる一方で、論評の仕方が多様であるのには、いささか困惑もした。それぞれがいくらかすれちがっていて、論評同士を組み合わせてみても、論争に発展しそうにない。論評というよりも、個々や集団の、立場の表明のようなものも多い。
これはいってみれば異種格闘技みたいなもので、土俵あり、リングあり、フィールドあり。総じて論壇を形造っていないのである。それぞれの論評から事実の要素を抜き出すことはできても、論評そのものが参考になるものは少なかったとわたしは思う。
しかしこのスピーチについては、さまざまな面からの分析が必要であろう。問題はそれをどうやって統合するかなのだが、今回の場合、訪問そのものからして、とりわけ多様な意味を含んでいたということも確かである。
広島に、原爆投下国の大統領がはじめて来るということ。これはスピーチの内容をはるかに凌ぐ最大のシグナルだった。このためにどれだけの根回しが必要だったか、勉強をしたか、勇気が要ったかは次第に判ることだろう。
また時代が経つと、そのスピーチよりも、オバマ氏が広島平和記念資料館を参観したという事実の方が、高い価値を持つかもしれない。
そして重要なのは、オバマ氏が広島にのみ集中したわけではなかったということ。同じくアメリカが大量の爆弾を投下したベトナムをまず訪問し、そして志摩のサミットに参加し、軍人として岩国ベースを経て、そして広島に来たのである。この一連の行動に含まれる外交的シグナルも見落すべきではない。
日米越の深い和解と協調の表明。広島において、広島とアジアと世界を語ったのである。またスピーチ(文面)にもあったようにテロ国家、テロ集団への警戒の呼びかけ。新しい時代の戦争への注意喚起。
冒頭では、親子のたとえを持ち出したが、このスピーチがオバマ大統領にとって軍縮スピーチの「末の子供」だとすれば、「第一子」としてのプラハスピーチがある。多くの人は、プラハスピーチと比較して、広島スピーチには具体性が欠けるといって矛盾を突くけれども、任期も残りわずかとなった大統領は、この広島においては追悼を第一とするために、理念の伝達にむしろ専念したということではなかろうか。これは好意的に過ぎるであろうか。
ただオバマ氏の意図はどうであれ、現代のわれわれは、歴史的事実として、プラハ広島の両スピーチの長所を選んで活かすべきなのであろう。今後このスピーチの価値を決めるのは、オバマ氏だけでもなく、アメリカだけでもないのだから。
オバマ氏にしても今現在の評価よりも、将来を期してのスピーチであったろう。それは文面からもうかがえる。このスピーチと、オバマ氏と、アメリカは、まもなくそのあまりにも強い絆から離れ、それぞれの運命を生きてゆかねばならない。その点からすれば、大統領のスピーチと謂わんよりも、すでにノーベル平和賞受賞者としてのスピーチであったのかもしれない。
いずれにせよこのスピーチは生れたばかりだ。この子供が今後どんな人間になるのかというのは、即断することができない。また本人の意志もさることながら、環境というものもある。もしこの夏から秋にかけて、アメリカが大規模な軍事行動に出たとすれば、このスピーチはそのための偽装だったとさえ言われかねない。(これはスピーチではないが、1938年秋、独伊はむろんのこと、仏英でもほとんど熱狂的に歓迎されたミュンヘン会談の結果が、実際は平和の礎ではさらさらなく、地獄の入り口であること、これを西欧が理解するまで、多くの時間を必要とはしなかった。羊の皮は半年とすこしで剥げたのである。)
ところでオバマ氏はやはり演説、スピーチの名手で、その要諦のひとつに、聴衆との間合いがあるのではないかと思う。その点からすれば5月27日の広島でのスピーチでは、参加者に同時通訳のイヤーフォンを配るよりも、むしろ逐次通訳を立てるべきであったろう。
録画で確認していただければと思うが、彼は、その冒頭、「71年前、」という語りかけとちがって、スピーチの中間部分ではあきらかに緊張していた。はじまって10分を過ぎたあたり、声のピッチは上がり、つまりうわずっていた。語数は増えて早くなり、だが声は小さくなっていた。一語一語に対する反応を掴めなかったからなのであろう。
いまとなっては逐次通訳は古風ではあるが、聴衆の反応を確かめることに関しては有利な場合もある。この日もしそうであったなら、彼も通訳が喋っている間、複数の聴衆とアイコンタクトをとることもできて、落ち着いたスピーチになったことだろう。
さらに言えば、このスピーチには、(それが直前に仕上げられたものであっても)確定原稿があったはずだから、この訳を、大統領と交代に読む役を、日本の首相か外相が受け持っていたなら、さらにどれだけ効果があったろう。諸国から寄せられる好意のコメントや、また反発は、比較にならないほど大きかっただろう。(しかしこの広島に至るまで、アメリカ政府ではきわめて慎重に検討が重ねられていたはずで、とても日本を巻き込んだ演出にまでは至らなかっただろうが。)
だがなんといってもこの訪問とスピーチは、現代の世界にとっては貴重な種子なのだ。貶すにしても、称えるにしても、1ヶ月後、1年後、願わくば10年後にも、この広島訪問とスピーチが忘れられることなく、そしておだやかに話題にのぼる世界であることを、心底から望むし、またそうあらねばと、わたしは思う。
2016/06/06
若井 朝彦(書籍編集)
目 次 (若井 記事) 索 引 (若井 記事)